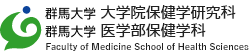保健学研究科保健学専攻 博士前期課程の特徴
近年、グローバルな感染症の拡大、高齢化社会、生活習慣病、医療者の地域偏在など、人々が健康を維持するための課題が急速に拡大しています。これらに対して、保健学研究科は人々の健康に対する保健システムの観点から健康を探究していきます。
博士前期課程では、保健学の基礎的な分野を扱う「基礎保健学ユニット」、保健学研究の成果を疾患治療に応用する分野を扱う「応用保健学ユニット」、そして地域の問題や国際的な分野を扱う「地域・国際保健学ユニット」の3ユニットが設置されています。学生は、「看護学領域」、「生体情報検査科学学領域」、「リハビリテーション学領域」の専門領域によって更に区分される9つの分野のいずれかに所属しますが、専門領域にかかわらず各ユニットのコア科目の履修が義務づけられており、職種専門領域を横断する教育システムによって保健学を包括的に研究することを当研究科の特徴としています。 その他に、がん看護、老人看護、慢性疾患看護および母性看護の専門看護師養成コースや、指導的臨床研究コーディネーター管理者養成コースも開設しています。
| ユニット | 看護学領域 |
|---|---|
| 基礎保健学ユニット | 基礎看護学分野 |
| 応用保健学ユニット | 応用看護学分野 |
| 地域・国際保健学ユニット | 地域・国際看護学分野 |
| ユニット | 生体情報検査科学領域 |
|---|---|
| 基礎保健学ユニット | 基礎生体情報検査科学分野 |
| 応用保健学ユニット | 応用生体情報検査科学分野 |
| 地域・国際保健学ユニット | 地域・国際生体情報検査科学分野 |
| ユニット | リハビリテーション学領域 |
|---|---|
| 基礎保健学ユニット | 基礎リハビリテーション学分野 |
| 応用保健学ユニット | 応用リハビリテーション学分野 |
| 地域・国際保健学ユニット | 地域・国際リハビリテーション学分野 |
博士前期課程各ユニットの特色
基礎保健学ユニット
(基礎看護学分野/基礎生体情報検査科学分野/基礎リハビリテーション学分野)

保健学全般に共通する理論、技術の構築、開発と評価、さらに保健管理における諸課題を対象とした研究及び教育を行う。また、分子情報の解析などの検査技術の開発やリハビリテーションの対象となる生体運動・精神機能の分析方法などの基盤的保健学教育及び研究指導を行う。ここで扱う研究は保健サービスの人的あるいは物的な管理の向上、また保健課題に対しての分析方法や、それから得られた情報の有効利用を目指すものであり、WHO の提唱する保健システム強化アプローチの「サービスの提供」や「情報」に合致するものである。
応用保健学ユニット
(応用看護学分野/応用生体情報検査科学分野/応用リハビリテーション学分野)
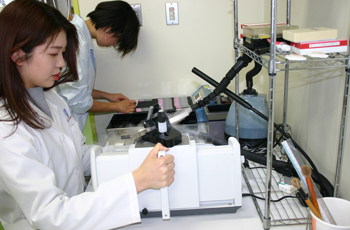
がん、慢性病、精神疾患や母性・小児疾患の看護やケア、心電図などの生理学的検査や病理診断技術、あるいはスポーツや作業活動に対するリハビリテーションなど保健学研究の成果を疾患・障害に対する治療に応用する分野の研究及び教育指導を行う。病を持つ人の適応、効果的な看護技術や効果的なリハビリテーション技術の検証と開発及び疾患検査法の開発などが含まれる。さらに、高度専門医療人である専門看護師(慢性疾患看護、がん看護、母性看護)及び臨床研究コーディネーター管理者の教育、養成を行う。ここで扱う研究は効果的臨床応用を目指して保健医療の知識・技術を高めるものであり、WHO の提唱する保健システム強化アプローチの「医療技術」に合致するものである。
地域・国際保健学ユニット
(地域・国際看護学分野/地域・国際生体情報検査科学分野/地域・国際リハビリテーション学分野)

地域で生活する個人、家族、集団及び地域社会全体を対象とした保健学知識、技術に関する教育及び研究を指導する。また、国際保健学分野における諸課題を対象とした教育及び研究指導を行う。さらにチーム医療教育機関のネットワーク Japan Interprofessional Working and Education Network (JIPWEN) を活用し、国際的多職種連携医療教育を推進する。ここでは地域医療の崩壊に伴う諸課題を、地域から、そして国際社会の観点から研究するものであり、WHO の提唱する保健システム強化アプローチの「保健人材」に合致するものである。またここでは、超高齢化地域の諸課題に対応する老年看護を実践する高度専門医療人である専門看護師(老人看護)の教育・養成を行う。
保健学研究科保健学専攻 博士後期課程の特徴
博士後期課程では、基礎、応用、地域・国際の3教育研究分野によって縦に構成された看護学領域、生体情報検査科学領域、リハビリテーション学領域の3つの領域から構成されており、各領域の教育研究分野において、それぞれ独自の学問体系を確立するための独創的な教育・研究を進めると同時に、それぞれの領域間を有機的に結びつける学際 的な研究を展開することができるよう工夫されています。
- 共通コア科目では、教育・研究に必要な原理・方法、国際保健医療推進に必要な能力を修得すると 同時に、医学・保健学領域の最先端の情報を得ることで、これからの保健医療・福祉の実践、教育 研究の進むべき方向について学修します。
- 専門教育科目では、教育研究分野に即した最新の保健医療・福祉に関する情報を修得するとともに 教育・研究の現状と問題点の把握、独創性の高い研究論文精読を通して研究の着眼点や展開法を学 修します。
- 特別研究では、それぞれの領域で独創性の高い研究を進めるために必要な研究計画、研究方法、研 究結果の解読力及び考察力を養い、与えられた課題について、学生自らが博士号に相応しい研究論 文を完成させ、国内外の学会で発表するよう指導します。
| 看護学領域 |
|---|
| 基礎看護学分野 |
| 応用看護学分野 |
| 地域・国際看護学分野 |
| 生体情報検査科学領域 |
|---|
| 基礎生体情報検査科学分野 |
| 応用生体情報検査科学分野 |
| 地域・国際生体情報検査科学分野 |
| リハビリテーション学領域 |
|---|
| 基礎リハビリテーション学分野 |
| 応用リハビリテーション学分野 |
| 地域・国際リハビリテーション学分野 |
博士後期課程各領域の特色
看護学領域
(基礎看護学分野/応用看護学分野/地域・国際看護学分野)
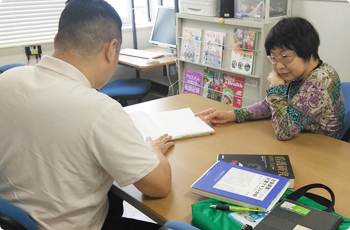
それゆえ看護学領域の使命は、ストレス緩和と健康生活の維持のためセルフケア能力を高める支援、疾病と共に歩む人々の QOL を高める支援、在宅療養者・高齢者・小児とその介護者や養育者への支援、周産期母子看護、地域や海外で展開される保健医療活動の支援についての課題を探求し、未知の現象の解明、新しい看護実践の技術、ケアシステムを開発することである。手法としては自然科学的アプローチと人間学的アプローチを用いる。また、多職種と連携する保健医療福祉活動において自らの専門性を発揮するとともに、多職種間のマネジメント、調整、相談、教育に能力を発揮し、協働的研究に参画できる高度実践看護専門職を養成する。
生体情報検査科学領域
(基礎生体情報検査科学分野/応用生体情報検査科学分野/地域・国際生体情報検査科学分野)
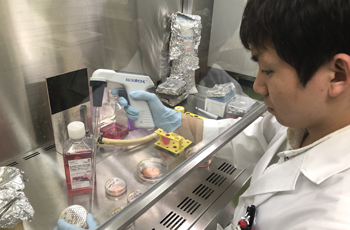
続いて、生体に生じる種々な疾病による組織学的・細胞学的変化や血液細胞の形態・動態の変化を免疫組織化学的及び分子生物的な最先端の技法を用いて解析し、疾病の解明に応用する能力や新しい検査技術開発のための研究をする。そして、病理学的検査・細胞学的検査、血液学的検査に精通した専門的知識と能力の養成を行う。
さらに、新興・再興感染症等と生体防御機構との関わりや病原生物の特殊検査法開発等の教育・研究を行う。また、環境保健の情報から得られた様々な研究成果に基づき、国際・地域の保健対策と評価を実践できる専門職の養成を目指す。更に、開発途上国の国際感染症等の新検査法についての研究や保健対策を実施できる能力を養成する。
リハビリテーション学領域
(基礎リハビリテーション学分野/応用リハビリテーション学分野/ 地域・国際リハビリテーション学分野)

リハビリテーション学は、これらの問題分析や基礎・応用的介入理論と技術の開発、地域及び社会環境の分析と対応といった包括的な科学としての特色を持つ。また、リハビリテーション学の特性から、保健医療・福祉に関わる専門職者を積極的に受け入れ、学際的な研究・教育者を養成することを特色とする。